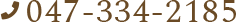不正咬合の種類と特徴
- コラム
不正咬合の種類と特徴
不正咬合は、正しい噛み合わせがされていない状態を指します。これは、歯に関連する問題だと思われがちですが、実際には歯の配置だけでなく、顎の成長にも影響されることが多く、指しゃぶりや舌癖なども影響を及ぼすことがあります。不正咬合の種類によっては、遺伝的要因が重要な役割を果たすこともあるのです。
不正咬合は、咀嚼、発音、顎の成長、そして顎関節に不良な影響を及ぼす可能性があるだけでなく、外見に関する心理的な悪影響も引き起こす可能性があります。
不正咬合の種類
不正咬合には、一般的に以下のような種類が存在します。不正咬合のタイプに応じて、その原因や可能な影響には差異が見られます。
叢生(そうせい)
叢生歯は、歯がバラバラな方向に生えており、歯列の一部に凹凸や重なりが見られる状態を指します。この状態は、顎の大きさと歯の大きさのバランスが悪いために発生し、歯が適切に配置されるスペースが不足していることが原因とされています。厚生労働省の「歯科疾患実態調査」によれば、日本人の不正咬合の割合において、叢生歯が最も多く、全体の4割を占めています。なお、「八重歯」も叢生歯の一種として含まれます。
空隙歯列(くうげきしれつ)
空隙歯列歯は、歯と歯の間に隙間やすき間ができている状態を指し、「すきっ歯」とも呼ばれます。この状態は、顎の大きさに対して歯が小さく、または歯の本数が不足していることが原因となります。空隙歯列歯になると、サ行やタ行などの発音が不明瞭になる可能性があり、また、歯の間に食べ物や汚れがたまりやすく、虫歯や歯周病のリスクが高まることがあります。症状の程度に応じて、一部の場合には矯正治療によって改善できることもあります。
上顎前突(じょうがくぜんとつ)
上顎前突は、上顎前歯や上顎全体が前方に突き出している状態を指し、一般的には「出っ歯」として知られています。この状態になると、口を閉じにくくなり、口呼吸や口の乾燥が起こりやすく、それに伴い口臭や虫歯、歯周病などのリスクが増加します。また、見た目に不安を感じる人も多く、精神的な影響も考慮されます。上顎前突は遺伝的要因が影響することがありますが、指しゃぶりや舌癖などの後天的な要因も関与することがあります。
下顎前突(かがくぜんとつ)
下顎前突は、一般的に「受け口」や「反対咬合」とも称され、下顎前歯または下顎全体が前方に突き出ている状態を指します。この状態では、咀嚼機能が低下し、また「サ行」などの発音が不明瞭になるなど、さまざまな不都合が生じる可能性があります。下顎前突の原因には、遺伝的要因に加えて、舌癖や口呼吸などの後天的な要因も関与することがあります。下顎前突の状態では、正常な顎の成長が阻害される可能性が高く、症状の悪化が懸念されます。
開咬(かいこう)
開咬は、一般的に「オーブンバイト」とも呼ばれ、前歯が噛み合わず、常に前歯部分が開いた状態を指します。この状態では、前歯を使って噛むことができず、代わりに奥歯に過度な負担がかかることがあります。それに伴い口の中が乾燥しやすく、滑舌が悪化するなどの悪影響が生じることがあります。開咬の原因には、哺乳瓶やおしゃぶりの長期的な使用、指しゃぶり、またよく噛まない習慣などが挙げられます。
過蓋咬合(かがいこうごう)
過蓋咬合は、上下の歯の咬み合わせが非常に深くなっている状態を指し、「ディープバイト」とも呼ばれます。この状態では、噛み合わせた際に下の前歯がほとんど見えないように上の歯が覆い隠してしまいます。前歯でしっかりと噛むことができず、それに伴って虫歯や歯周病、顎関節症などのリスクが高まることがあります。過蓋咬合の原因はさまざまであり、上顎と下顎の大きさのバランスが不適切なことなどが考えられます。
このような症状ありませんか?
不正咬合により起こる主な3つの症状
「生え変わりによって自然に治るだろう」と考えて放置するケースも一部存在しますが、実際には自然治癒しないケースの方が一般的です(不正咬合のタイプにより異なります)。
特にお子様の場合、顎の成長段階で早期に治療を始めることで、治療期間を短縮したり、治療の負担を軽減したりできる場合もあるため、以下のような症状に気付いた場合は、受診をお勧めします。
・口呼吸
口呼吸は、口内の乾燥を引き起こし、虫歯や歯周病のリスクを高めるだけでなく、口臭、風邪、睡眠時無呼吸症候群、アレルギーなどのリスクも増加させる要因となります。さらに、口が開いたままの状態が続くと、前歯が前に出やすく、不正咬合を進行させる原因ともなります。
・常に口が開いている
口が開いたままの状態が続くと、口周りの筋肉の発達が妨げられます。唇をしっかり閉じる筋肉が発達しないと、口を閉じるのが難しくなり、悪循環が生じます。また、これにより姿勢にも影響を与え、前かがみになりやすく、背骨にも悪影響を及ぼす可能性があります。
・食事時によく噛まない
十分に噛まないことは、口周りの筋肉や顎の発達に不利益をもたらし、不正咬合の要因となります。不正咬合が進行すると、歯が正しく噛み合わないため、よく噛むことが難しくなり、早食いの習慣を持ちやすくなります。よく噛まないことは、不正咬合の原因であり、不正咬合に関連した症状の一つでもあります。